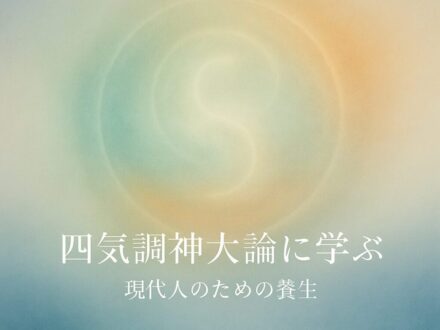第2回 黄帝内経素問 上古天真論篇 ― 古代人と現代人の違い
前回の記事
導入 ― 二千年前から続く問い
「昔の人は百歳を超えて生きていたのに、今の人は五十歳で衰えるのはなぜか?」
黄帝のこの問いかけに、岐伯は明快に答えました。
古代人は自然と調和して生きていたからこそ長寿であり、現代人(当時の人々)は欲望に溺れ、精気を失うから短命になったのだ、と。
ここでは、岐伯が語る古代人と現代人の違いを、生活習慣・心の持ち方・養生観の三つの視点から見ていきます。
古代人の生き方 ― 自然とともにある暮らし
岐伯が語る古代人は、まさに「自然に生きる人」でした。
- 日の出とともに起き、日の入りとともに休む
昼夜のリズムを乱さず、陰陽の調和を保つ。 - 春夏秋冬の移ろいに合わせて行動を変える
春には伸びやかに、夏は旺盛に、秋は収め、冬は静かに。 - 飲食に節度を持ち、欲望に溺れない
腹八分を守り、過食や過飲をしない。
こうして古代人は「腎精」を大切に保ち、精気を充実させ、百歳を超えても衰えることなく生きられたといいます。
現代人の生き方 ― 精気を消耗する暮らし
一方、岐伯が批判した「今の人」は、自然に背を向け、欲望に流された生活をしていました。
- 酒を好み、過度に酔いに溺れる
肝を傷つけ、精気を失う。 - 色欲に流され、生命力を消耗する
生殖に関わる精気を浪費し、腎を弱める。 - 夜更かしや不規則な生活
昼夜の陰陽のバランスを崩し、体のリズムを乱す。
その結果、五十歳前後で体が衰え、老化が早まってしまう。
これは古代の記録でありながら、現代の私たちの生活にもそのまま当てはまる部分が多いことに驚かされます。
精気を守るという考え方
『黄帝内経』では、生命の根本を「精」と表現します。
腎に蓄えられるこの精が、気や血の源となり、全身の健康を支えています。
- 古代人は精を守る生活をした → 長寿
- 今の人は精を失う生活をした → 短命
このシンプルな対比が、養生の核心なのです。
心のあり方の違い
古代人は心を静かに保ち、過度な感情の起伏を避けました。
現代人は快楽や刺激を求め、感情に翻弄されやすくなっています。
- 怒りは肝を傷つける
- 憂いは脾を弱める
- 恐れは腎を損なう
感情と臓腑の関係を重視する東洋医学において、心を安定させることは養生の基本でした。
岐伯の示した対比の意味
黄帝と岐伯の対話は「昔はよかった、今は悪い」という単純な話ではありません。
大切なのは「自然に従うか、それに逆らうか」という姿勢の違いです。
自然に従えば精気は満ち、長寿になる。
自然に背を向ければ精気は減り、早く衰える。
この普遍的な原則を、岐伯はシンプルに伝えているのです。
現代に生かす視点
現代社会でも、岐伯の教えは活かせます。
- 夜更かしや不規則な生活を避ける
- 飲食に節度を守る(ファストフードや過度な糖分を控える)
- ストレスや感情の起伏をコントロールする
- 季節ごとに生活リズムを調整する
便利さや快楽を追い求めすぎれば、体は確実に精気を失います。
逆に少しの意識で、古代人のように長く健やかに生きる力を養うことができます。
まとめ
古代人は自然と調和して精気を守り、現代人は欲望に流され精気を失った。その違いが寿命の差を生んだ。
【関連記事一覧】
第1回:古代人はなぜ長寿だったのか?
第3回:養生の基本原則
第4回:女性のライフサイクル 七の倍数
第5回:男性のライフサイクル 八の倍数
第6回:例外的な長寿者
第7回:養生の理想像 真人・至人・聖人・賢人
第8回:養生が教える病を防ぐ生き方