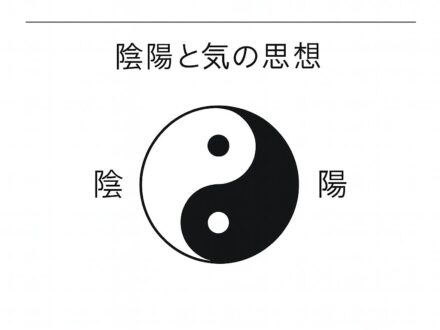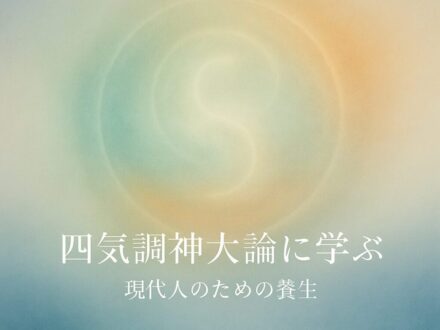第3回 黄帝内経素問 上古天真論篇 ― 養生の基本原則
前回の記事
目次
導入 ― 養生とは何か?
第1回・第2回では、古代人と現代人の寿命の差や生活習慣の違いを見てきました。
そこから浮かび上がるのは「養生」という概念の大切さです。
『黄帝内経』の上古天真論篇では、養生の要点を大きく三つにまとめています。
それが 陰陽の調和・精気の保持・精神の安定 です。
ここでは、その三本柱を掘り下げ、現代の私たちがどのように活かせるのかを考えてみます。
陰陽の調和 ― 自然のリズムに従う
東洋医学の根本思想は「陰陽調和」です。
昼と夜、寒と熱、動と静――これらがバランスを保つことで生命は安定します。
四季に従う
- 春:体を伸びやかにし、陽気を取り込む
- 夏:活動的に過ごし、発散を大切にする
- 秋:引き締めに転じ、収穫と調整を意識する
- 冬:静かに休み、精気を養う
この四季の流れは、体内の陰陽の変化とも呼応しています。
昼夜のリズム
夜は休む時間であり、精気を回復させるとき。
無理に夜更かしをすると陰陽の調和が崩れ、病の原因になります。
👉 現代では「睡眠の質」が健康寿命を大きく左右する要素となっており、まさに古代の教えと一致しています。
精気の保持 ― 腎精を守る生き方
『黄帝内経』は「腎精(じんせい)」を生命の根本と捉えます。
精は気と血を生み出し、成長や生殖、免疫力の基盤となります。
精を消耗しない工夫
- 暴飲暴食を避ける
- 性生活の節度を守る
- 過労を避け、適度に休養する
精を養う工夫
- 季節の食材を取り入れる
- 穀物・野菜を中心にバランスよく食べる
- 十分な睡眠をとる
👉 精気を「使いすぎないこと」「補うこと」の両方が重要なのです。
精神の安定 ― 心を乱さない
『黄帝内経』では、感情の偏りが臓腑を傷つけると説きます。
- 怒りすぎ → 肝を傷つける
- 喜びすぎ → 心を傷つける
- 思い悩みすぎ → 脾を傷つける
- 悲しみすぎ → 肺を傷つける
- 恐れすぎ → 腎を傷つける
心が乱れると気血の巡りが悪くなり、病を生む。
だからこそ「心を静かに保つこと」が養生の基本です。
現代的な実践
- 深呼吸や瞑想で心を整える
- 自然の中で過ごす時間を持つ
- デジタル機器から離れる「デジタルデトックス」
こうした工夫は、精神を安定させると同時に精気を守ることにもつながります。
養生の三本柱をまとめると
- 陰陽の調和 → 自然のリズムに従う
- 精気の保持 → 腎精を守り、無駄に消耗しない
- 精神の安定 → 心を整え、過度な感情に支配されない
この三つは互いに支え合い、どれか一つが欠けても健康は成り立ちません。
現代に活かすヒント
養生の三本柱を、現代人の生活に落とし込むと次のようになります。
- 睡眠のリズムを整える(陰陽の調和)
- 腹八分目とバランスの取れた食事(精気の保持)
- ストレスマネジメントを行い心を整える(精神の安定)
古代人が実践していた「自然に従う生活」は、科学的に見ても理にかなった健康法であることが分かります。
まとめ
養生の基本は「陰陽の調和」「精気の保持」「精神の安定」の三本柱である。
【過去の回一覧】
第1回:古代人はなぜ長寿だったのか?
第2回:古代人と現代人の違い
第4回:女性のライフサイクル 七の倍数
第5回:男性のライフサイクル 八の倍数
第6回:例外的な長寿者
第7回:養生の理想像 真人・至人・聖人・賢人
第8回:養生が教える病を防ぐ生き方