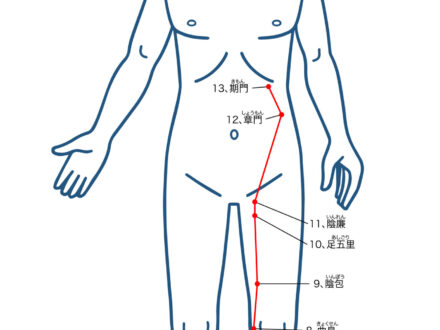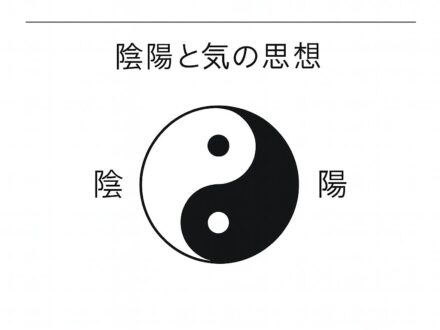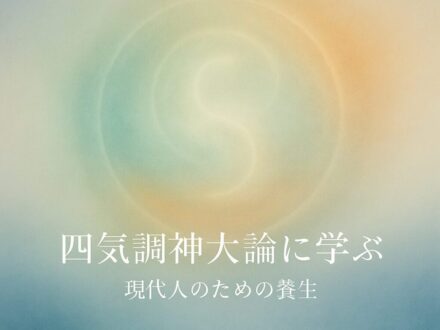第7回 黄帝内経素問 上古天真論篇 ― 養生の理想像 真人・至人・聖人・賢人とは
前回の記事
導入 ― 養生の究極の姿
『黄帝内経』上古天真論篇は、養生の究極の理想像を四つのタイプにまとめています。
それが 真人(しんじん)・至人(しじん)・聖人(せいじん)・賢人(けんじん) です。
彼らはただ長生きをするだけでなく、自然と調和し、心身を自在に保ちながら暮らす人物像として描かれています。
真人 ― 自然と一体化した存在
真人とは「真に人である者」。
自然と完全に調和し、四季の変化に従って生活します。
- 四季の気候に逆らわない
- 喜怒哀楽に振り回されない
- 精気を損なうことなく長寿をまっとうする
まるで仙人のように、天と地のリズムに生きる姿が描かれています。
至人 ― 究極に達した人
至人とは「至る者」、すなわち養生の道を究めた人物です。
- 外界の変化に動じず、内面の静けさを保つ
- 食欲や性欲などの本能を節度で保つ
- 生命力が満ち、病にかかることが少ない
至人は「心の安定」に重きを置いた存在像といえるでしょう。
聖人 ― 知恵と徳を備えた人
聖人は、知恵と徳を兼ね備え、社会の中で人々を導く存在です。
- 自分の健康を保ちながら、周囲にもよい影響を与える
- 養生を実践することで社会秩序を保つ
- 他者を助け、調和をもたらす
聖人は単なる個人の健康を超え、社会的役割を果たす存在として描かれています。
賢人 ― 知恵を活かす人
賢人は、現実的な知恵を持ち、日常生活に養生を活かす人です。
- 過度な無理をせず、生活を工夫して健やかに暮らす
- 知識を積み重ね、経験をもとに人々を導く
- 理想に届かなくても、現実的に実践できる生き方を重視する
賢人は、最も私たちに近いモデルかもしれません。
四つの理想像が示すこと
真人・至人・聖人・賢人という四つの人物像は、それぞれレベルや役割が異なります。
しかし共通しているのは「自然に従い、精気を守り、心を安定させること」です。
これは第3回で触れた「養生の三本柱」と重なります。
現代に活かす視点
- 真人 → 自然のリズムに生きる(規則正しい生活)
- 至人 → 心の静けさを大切にする(瞑想・マインドフルネス)
- 聖人 → 健康を社会に役立てる(周囲を支える)
- 賢人 → 日常で無理なく養生を実践する
それぞれの理想像を現代に置き換えると、私たちにも実践可能な指針となります。
まとめ
養生の理想像として「真人・至人・聖人・賢人」が示され、いずれも自然に従い精気を守る生き方を体現している。
【過去の回一覧】
第1回:古代人はなぜ長寿だったのか?
第2回:古代人と現代人の違い
第3回:養生の基本原則
第4回:女性のライフサイクル 七の倍数
第5回:男性のライフサイクル 八の倍数
第6回:例外的な長寿者
第8回:養生が教える病を防ぐ生き方