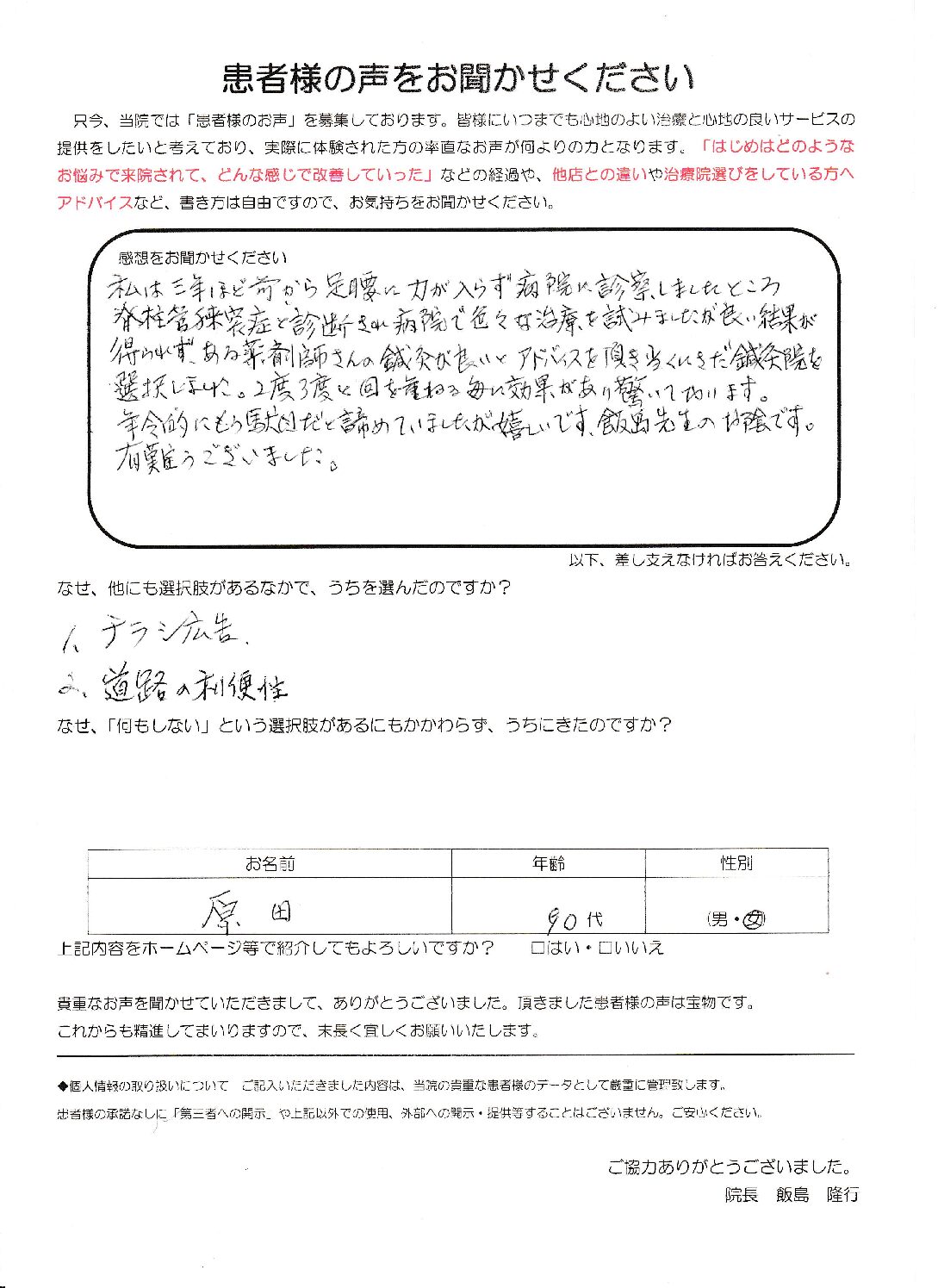腰痛が治らない理由
こんなお悩みございませんか?
- 腰をかがめるたびに痛くて泣きたくなる
- 痛みが出るのがわかっているから立っている状態が多い
- マッサージなどで腰をぐいぐいおされて余計に痛くなった
- 慢性腰痛である
- グキッとやってしまった
- 繰り返す痛み
腰痛は、種々の原因により腰部、腰部から下肢にかけて痛みを有する症状です。
腰痛をきたす疾患を原因から分類すると
椎間板、脊柱の構築上の異常、加齢、軟部組織の異常、炎症、加齢、などがあげられます。
腰痛が治らない原因はなんとなくごまかして、腰に負担をかけつつ、ぎりぎりのところで痛みが出ないように保って生活しているからだと考えています、人間の体は、何十年も長期使用しているとだんだんと痛みに鈍感になってしまいます。
特に腰部は上半身と下半身をつなぐ肝心要であるにもかかわらず、無理がきいてしまうという、頼もしいんだか危険なんだか複雑な性質をもってます、二足歩行脊椎動物である人類は地球の重力にさからっているが故、他の動物に比べて、比べ物にならないくらい特にです。
さて、腰痛といっても様々な腰痛があります
一般的によくいう腰痛から私の解釈含めた説明をさせていただきます。
腰痛とは…

動作時や安静時もしくはその両方で痛みだるさを感じる症状の総称です。とても漠然としていますね。
腰痛を引き起こしている原因として病院のお得意な画像診断等で特定しやすいものは骨、その骨の関節、骨の衝撃を和らげるクッションや、骨と筋肉をつなぎとめる靭帯などによるなんらかの不調や変形が考えられます。
しかし画像診断等で、症状を引き起こしている原因を特定できるのは実に三分の一以下と言われています。
画像診断(MRI)で特定できる病態を挙げていきます
腰部の椎間板ヘルニア(腰の骨と骨の間のクッションである椎間板が出てしまう症状)
腰部脊柱管狭窄症(腰の骨の中心の神経を通している脊柱管という脊髄を通している管の部分が狭くなる)
レントゲンで特定できる病態として
腰部変形性脊椎症(骨と骨の間のクッションが加齢により狭く薄くなる)
これらの変性は加齢によるものが大きいため確かに診断数は限られてくると思われます。
しかも最近の腰痛に対する考え方として、脊椎症等が画像診断で確定されても痛みだるさしびれの全くない方が一定数いる一方、それらの所見がなくても症状の出ている方がいるというから驚きです。因果関係を否定されているお医者様も現在一定数いらっしゃるみたいですね。
私の考える主な腰痛因子としては、やはり脊椎動物(背骨のある動物)で唯一の完全二足歩行、更にはおしりをぺったりとくっつけて座る体勢を長時間連続で続けるという完全に重力の抵抗を腰部で受け止めてしまっていることによる圧迫(これが圧倒的に多い気がします)、更には腰部ひいては全身的な血行不良が、直接的に考えられる最大のわかりやすい原因であると思います。
肉体労働以上にデスクワーク等のパソコンの文字、数字と終日にらめっこを続けていらっしゃる方であれば思い当たる事、想像することは難くないと思われます。
画像検査で発見できる症状について少し書きましたが、他にも腰痛の症状といってもその症状のがどのような経過を辿って今に至ったのかによって数種類に分けることができます。
外傷による痛み
腰椎圧迫骨折…骨が外的圧力により押しつぶされる状態であり、もとの骨の形、受けた圧力の方向によって骨折は様々な形態をあらわします。他にも骨粗鬆症などによる脆さが原因となる場合もあります。
腰椎分離症…好発部位は第五腰椎(一番下の腰骨) 上の腰骨と下の腰骨をつなぐ椎弓が分離を起こしてしまった状態になります。
学生時代にスポーツをがんばりすぎて疲労骨折をおこした状態が残っている方に起こりやすく、男性は比較的若めの成人男性、女性は中年期に好発するようです。
要は使いすぎです。
痛み、症状は、腰部の鈍い痛み、疲労感を感じやすくなり。
神経痛は分離症によって起こることは考えにくいようです。
罹患部の背骨の棘突起という、背中から触れられるぼこっとした背骨の真上部分を押すと痛みが誘発されます。
腰椎すべり症…腰椎分離症が悪化し椎体(腰骨の本体)が前方にずれる状態を言います。
この場合、腰椎分離症では発生しなかった足腰のしびれ感が出てきます。
退行変性(加齢等)によるもの
腰椎椎間板ヘルニア…背骨と背骨の間のクッションの役割をはたしている椎間板という部分が、加齢(髄核の水分量減少による弾力性の低下)やその他の原因により圧迫等うけてクッションの内部の髄核(ずいかく)というゼリー状の椎間板の中身が、椎間板の外塀を構成している繊維輪を突き破り、脊髄や馬尾から左右後方に枝分かれしている神経根を圧迫してしびれ、痛み、筋力低下の脱力感等を引き起こします。
腰自体の痛み、腰から下(左右どちらか)の大腿(もも)下腿(ひざ下)足先、足底の痺れ感が出現する方がほとんどです。
痺れはいずれかの部位に限局的に出現する事がほとんどであり、痺れの出現部位によりヘルニアの位置を特定していきます。
大腿前面(ももの前側)からひざ下の前側、親指に痺れが出ているとき…腰骨の3番と4番の間のヘルニアを疑います。
向う脛(すね)に痺れが出ている場合…腰骨の4番と5番の間のヘルニアを疑います。 この位置のヘルニアが一番多い様です。
大腿後面(ももの真後ろ)からひざ下の後からかかとにかけての痺れ…腰骨の5番目から仙骨の移行部位を疑います。
以上、ヘルニアの好発部位上位3箇所を挙げました。
腰椎変形性脊椎症…主に誰にでも起こる、加齢による腰椎椎間板の変性や骨の増殖や変形などにより、場合によっては神経の圧迫を起こし痛みや運動制限を誘発します。
では腰痛の中でも最も多いと言われる、慢性型の腰痛について考えていきます。
「慢性」というのはこれ如何なる意味でどのような状態を示すのか…
慢性の腰痛とは、腰の痛みが発症してその痛みだるさが発症後1カ月から3カ月以上もしくはそれ以上の長期に及んだ場合の腰痛症を指します。
非特異的腰痛….画像診断、各種検査等で原因の特定できない腰痛の事をさします。
いわゆる原因不明という類ですね。
…. 厚生労働省による国民生活基礎調査(2015年度)における有訴者率で男の1位、女の2位を占める症状である(男の2位、女の1位は共に肩こり)。また、日本人の8割以上が生涯において腰痛を経験しているとされる。多くの人々は腰痛を訴えているが、画像診断で異常が認められない場合も多い。異常が認められる場合でも、それが腰痛の原因でないこともあり、腰痛患者の8割は原因が特定されていない
他、東洋医学では腰痛の大部分は腎の機能の低下、失調からくるものと考えられています。
腎の機能は精を蔵して水を主すると考えられていますが、これらの機能は内因によって変調をきたすことが多く、虚証(虚弱、加齢、ストレスなど)によるものが多いと考えられます。
ほか、外因(気候変動)による腰痛も挙げられます。
寒邪と湿邪という外因の邪によっておこる腰痛の場合
寒冷による腰痛の場合は腰が冷えて、腰から下の筋肉がこわばるため、温めると軽快するため、寒冷により悪化する腰痛です。
湿邪による腰痛は、腰が重く怠く、雨天や湿気の多い時期に増悪。梅雨時には湿熱の病態が出現して、イライラのストレスがたまり腰痛はさらに増悪します。
腎虚が原因の腰痛
腰部鈍痛、重い感じ、膝脱力、無力、膝屈伸困難、痛みの長期化、労作により憎悪、安静により緩和するといったことが慢性に何度も繰り返されるといった症状がみられる。
腎虚に加えて、体内の水分異常(腎陰虚)がみられる場合は、さらに手足のほてり、のぼせ、熱感、イライラ、不眠や不安感耳鳴りなども随伴症状としてあらわれます。
当院での改善法
腰痛に関しては上記の通り皮膚から腰の、一番深い箇所は成人男性で10センチほどの深さがあります。
当然ですが腰痛(慢性急性問わず)とは腰部の筋肉である大腰筋、腸腰筋などの体幹を支えたりする非常に丈夫で奥深く骨の際を走る筋肉の慢性使用、血流障害が原因で乾ききったスポンジのようにガチガチになってしまいます。
そのガチガチを改善に導くには、筋肉に血液をそそぎもとのしなやかな状態に戻してあげる必要があります。
筋、筋膜性腰痛、椎間関節性腰痛、腰椎椎間板ヘルニア、変形性腰椎症、ヘルニア、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、分離すべり症などの退行性変性である器質的な症状に対しては痛みや筋緊張を緩和する効果は鍼治療で高いものと考えられています。
器質的な変化によって生じた痛みやしびれ血行不良に対して抑制する働きをもつ効果をだしています。
当院では腰部の芯に届く鍼を用いて大腰筋、殿筋などの深くしつこく硬い筋肉に直接血流改善アプローチを行い、痛みなく曲げられる腰、伸ばせる腰に導きます。
他、東洋医学的な鍼灸治療
基本的な病態は寒邪(寒さによる人体への侵襲)湿邪(多湿による人体への侵襲)が腰部や下肢を巡行する経脈を侵襲して、気血の巡行を阻害した状態でおこる、基本的には寒、湿を散らして気血巡行を通す目的で、経絡上の圧痛点、反応点に鍼、灸を行います。
腎の障害も腰痛は起こりえます
生命活動の根本と考えられる腎は、虚すれば全身倦怠感、虚弱症状があらわれて、慢性的な腰背痛も出現します。
このような場合は腎気を補う鍼灸治療が必要になります。
命門(めいもん) 志室(ししつ) 太谿(たいけい) 関元(かんげん) といった基本穴をとって変化させていきます。