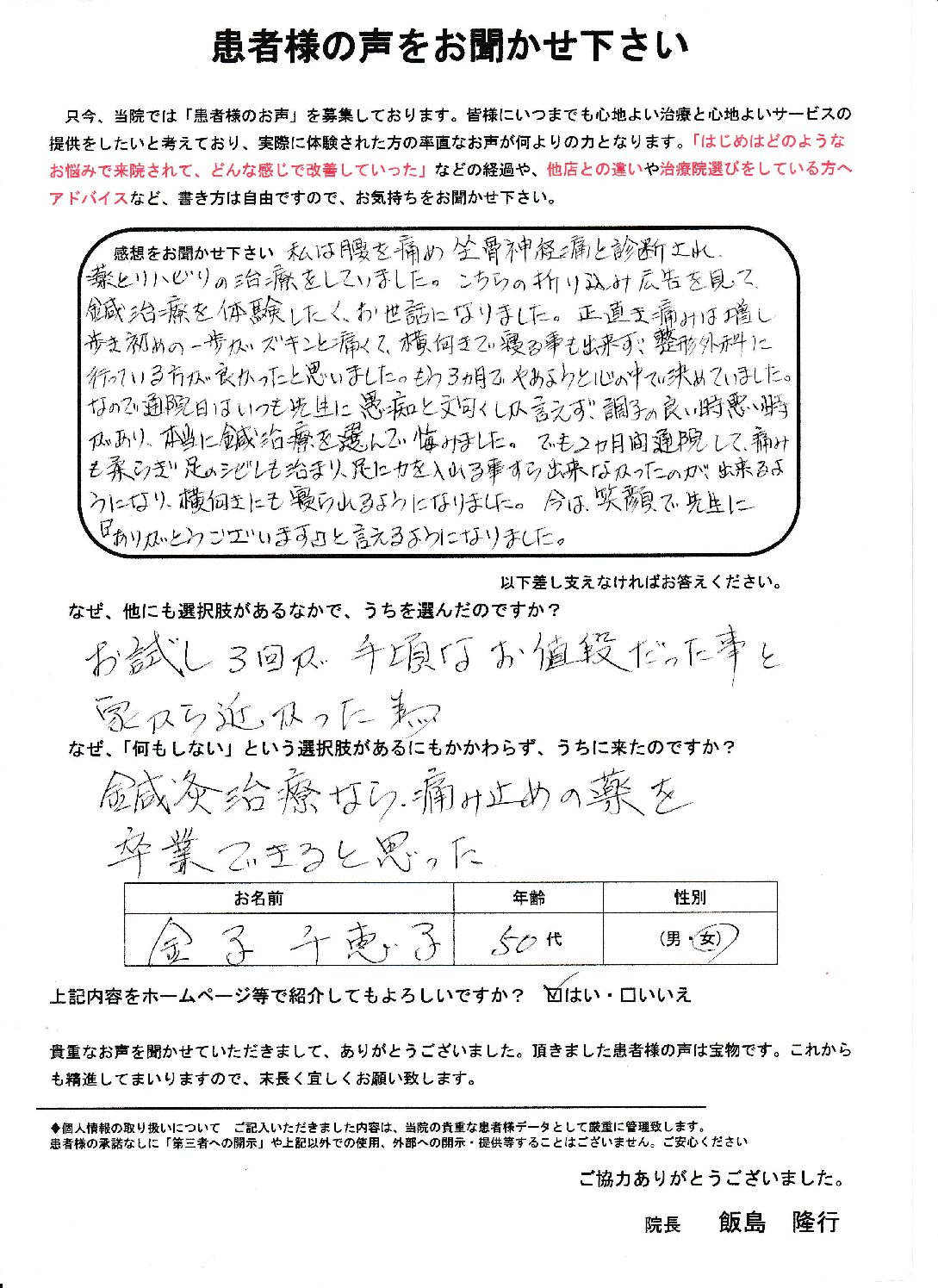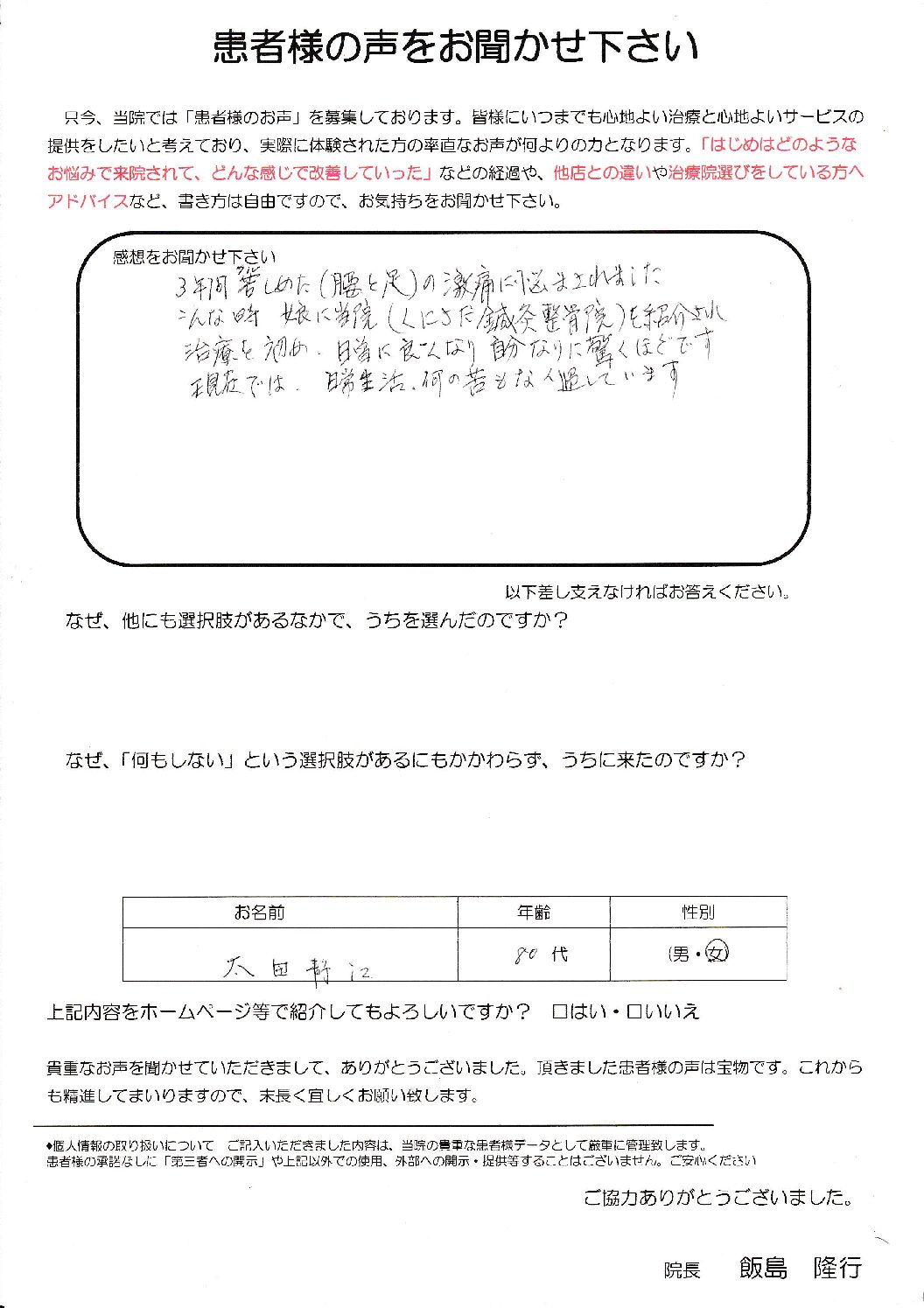脊柱管狭窄症が他で良くならない理由
このようなお悩みありませんか?
- 歩いていて数分で腰太もも足などに痛みがでる
- 痛みといっしょに痺れも出てくる
- 座って休憩していると痛くなくなるが、また歩くと痛くなる
- なかなか腰痛などの痛みがとれない
- 座っていれば痛くもなんともない
- たくさんの治療を受けたが良くならない

他でなかなか良くならない方の話を聞くと、今まで受けてきた施術は整形外科だと電気や温熱、牽引が多く、接骨院ではマッサージやストレッチを受けてきた方が多いのですが、このような施術ではあまり変化がなかったようです。
なぜこのような施術で変化がなかったかというと、原因をしっかりと把握したうえで根本改善ができていない、原因の脊柱管近接の深部筋肉自体へアプローチが届いておらず、外層の筋肉への圧迫刺激のみになり、血流改善をかえって阻害してしまい、結果繰り返し施術しても変化を感じない、もしくは悪化させてしまっているからです。
効果的ではないアプローチを受けた結果として症状が変化しない、悪化してしまうという悪循環を終わらせて、痛みや痺れに悩まない日常生活を送るためには原因である深部筋肉の硬さを改善する必要があるのです。
あなたの脊柱管狭窄症の症状がなかなか良くならない理由は、原因である深部筋肉への施術をしていなかったためかもしれません。
脊柱管狭窄症の症状について
一般的な解釈として脊柱管狭窄症は背骨の中の空洞(脊髄の通り道)が狭くなる症状により、末梢の馬尾神経や、神経根などが物理的に障害されることによって少し歩くと痛くて歩けないといった「間欠性跛行(かんけつせいはこう)」がおこってしまう症状のことを言います。
脊柱管狭窄症は、70代以降の比較的高齢の方にとても多く、整形外科などで手術を受ける方がとても多い症状です。
症状が進行してくると、泌尿器系にまで障害が及んでくることも見受けられます。
自覚症状として、痺れや足腰の脱力感や膀胱や直腸の泌尿器系のコントロールがうまくいかなくなるといった症状が後発します。
他にも足の腫れぼったく熱い感じといった感覚障害なども度々見受けられます。
脊柱管狭窄症の原因とは
症状を誘発させる原因は様々ですが、先天性(生まれながらの骨の形成)と、後天性(生活の中での変性、加齢による退行性変性)があります。
退行性変性とは、原因となる脊柱管の周辺の組織の変化(ヘルニア、腰椎すべり症)によって2次災害的に起こる変性をいいます。
それによって脊柱管の周りの血行障害が顕著になり、脊柱管狭窄症の症状が出てきてしまうものと考えています。
背骨の間のクッションである椎間板が加齢などの退行性変性で狭くなり、神経を刺激、圧迫することにより脊柱管狭窄症がおこります、座っていたり安静にしていれば神経を刺激することはないので、症状は起こりません、が、立ち上がったり、歩いたりすると椎間板の変性部分が神経を刺激してしまい脊柱管狭窄症の症状(間欠性跛行)を誘発してしまい、痺れ、痛み、歩けないといった状態をつくりだしてしまうのです。
当院ではこのように改善します
当院では主に、脊柱管狭窄症の狭窄している大本である腰椎中心部の血流障害や筋緊張の緩和、循環を整える鍼灸施術を行っています。
腰から下は、痛み痺れの走行上の経穴(ツボ)の沿って鍼を打ち、周辺筋肉の血流障害を緩和させています。
大腿部、下腿部や膝回りの好発部位に置鍼を施します。
鍼によって、副作用なく深部血流障害や、それによって起こっている筋硬結を改善して痛み感覚を緩和させることが可能です。
脊柱管狭窄症の方は体が冷えていることも多いため、東洋療術的な考えから血流の巡りを良くするような鍼灸施術をする場合もあります。