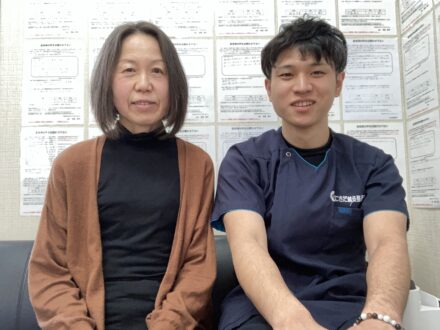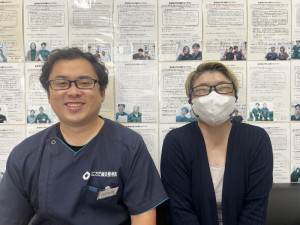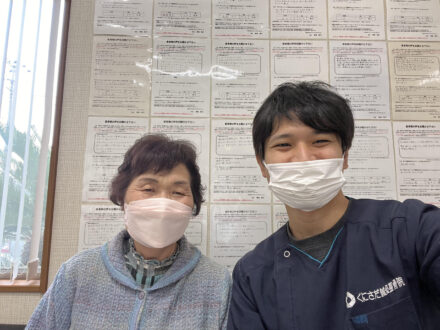【解説】「腕が上がらない!」「腕が後ろにまわらない!」「痛くて寝返りが打てない」、これって四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)です!

「洗濯物を干すときに腕が挙がらなくて困る」
「肩が挙がらなくて歯を磨いたり顔が洗えない」
「腕をおろしている時は何ともないけど、物を取ろうとしたときにズキンと痛くなる」
「車の運転中に後部座席に手を伸ばせない」
「夜中前触れもなく痛みで目が覚める事がある」
「肩が挙がらなくてゴルフができない」
これらの症状は、四十肩・五十肩(肩関節周囲炎)の典型的な症状として考えます。
深刻になると、「寝返りも打てない痛み」「筋力の低下」「手や腕のしびれなどの神経症状」が発生します。
しかし、患者さんの症状や訴えが似ていても、四十肩・五十肩の症状と原因は、お一人おひとり異なります。だから、痛みの取り方も、一人ひとり違うのです。
目次
- 1.肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の症状とは?
- (1)肩の動かしにくさ
- (2)肩の痛み
- (3)夜間痛
- (4)肩の硬直・可動域の制限
- (5)慢性的な痛みと肩こり感
- (6)反射的な痛み
- 2.肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)とは何か?
- (1)肩関節周囲炎とは?
- (2)症状の進行
- 3.なぜ、肩関節周囲炎になるのか?
- (1)肩関節周囲炎の科学的な研究
- (2)加齢による組織の変化
- (3)肩関節周囲の血流不足
- (4)慢性的な炎症と自己免疫反応
- (5)内因性の課題(内分泌系、代謝)
- (6)遺伝的要因
- (7)外的要因(過剰な使用や怪我)
- 4.肩関節周囲炎の初期の対策と予防法
- (1)初期の対策
- (2)予防方法
- 5.肩関節周囲炎の治し方
- (1)痛みの強い時期(急性期)
- (2)慢性期(痛みが落ち着いてきたら)
- (3)姿勢の改善
- 6.「肩関節周囲炎を治療する!」鍼灸院の選び方
- (1)肩関節周囲炎の専門知識と施術経験
- (2)実績や評判を確認する
- (3)丁寧な診断と治療方針の説明
- (4)運動療法や生活指導にも力を入れているか
- (5)自宅でできるケアのアドバイスがあるか
- (6)料金体系が明確であるか
- (7)一人ひとりに合わせた治療
1.肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の症状とは?

肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の主な症状は、肩の可動域制限や痛みを中心としています。以下は代表的な症状です。
(1)肩の動かしにくさ
腕を上げたり、後ろに回したりするのがぎこちなくなります。
肩に症状が集中します。背中に手を回す動きに制限がかかり、服を着替えたり、髪をセットするといった日常動作が困難になります。
(2)肩の痛み
初期には肩の前面や側面に鈍い痛みを感じることが目立ちます。肩を動かしたときに特定の角度で痛みが強くなることがあり、意識しない動作でズキッと痛みが走ることもあります。
(3)夜間痛
夜中に肩が痛みだしたりします。寝返りが打てないほどの強い痛みを訴える患者様も多いです。このため、眠りが浅くなり、睡眠不足に悩まされる人も少なくありません。
(4)肩の硬直・可動域の制限
肩関節の関節が硬くなって、可動域が制限されます。進行してしまうと「肩凍結」と呼ばれるほど、肩が固まって動かなくなることもあります。
こうなると物を取る動きや、車の運転中に後部座席に手を伸ばすような動作が難しくなります。
(5)慢性的な痛みと肩こり感
安静時でも違和感や鈍い痛み、肩こりを感じることが多くあります。肩から首や背中にかけての張りを感じることもあります。
(6)反射的な痛み
肩を動かした瞬間に反射的な痛みが走ることがあり、急な動きや伸びる動作がしづらくなります。
2.肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)とは何か?

(1)肩関節周囲炎とは?
肩関節を支える腱や靱帯、関節包などの炎症を起こし、肩の可動域が制限される疾患です。「四十肩」や「五十肩」とも呼ばれ、中高年に多く見られます。
肩関節周囲炎が発症する原因は、加齢に伴う肩関節周囲組織の異常(劣化)や疲労などによる血流の低下と考えられています。しかし、いまだに明確な原因がわからない場合も多い炎症です。また、代謝異常が影響して発症リスクが高まることもあるといわれています。
(2)症状の進行
肩関節周囲炎は一般的に以下の3段階で進行します。
- 痛み期:肩の動きで痛みが出始め、徐々に可動域が減ります。
- 凍結期間(半年〜1年):肩の稼働領域が大幅に制限され、「肩が凍りついたような」硬い直状態になり痛みもひどくなります。
- 回復期(数か月〜数年):徐々に痛みが軽減し、可動域が回復しますが、完全に元の状態に戻らないこともあります。
3.なぜ、肩関節周囲炎になるのか?

(1)肩関節周囲炎の科学的な研究
肩関節周囲炎の原因は完全には解明されていないもの、科学的な研究では加齢による組織の変性や肩関節周囲の血流不足で、肩関節周囲炎が発症するメカニズムに視点が向いています。
(2)加齢による組織の変化
肩関節周囲炎は主に40歳以降に発症率が高く、加齢とともに肩関節を構成する腱や靭帯、関節包(関節を包む袋状の組織)が劣化することがわかっています。すると、肩関節周囲の組織が硬くなり、可動性が低下しやすくなります。
特に肩の腱板(回旋筋腱板)や関節包はトラブルが多い部位で、劣化しやすいとされています。
(3)肩関節周囲の血流不足
肩周辺の血流は比較的少ないため、組織の修復や代謝が遅くなり、老化や疲労による損傷が軽くなりやすくなります。これが肩の柔軟性や可動域の低下、さらには痛みや固い原因になりますにつながります。
(4)慢性的な炎症と自己免疫反応
一部の研究では、肩関節周囲炎が自己免疫反応によって生じる可能性も示唆されています。炎症が慢性的に続いていることで、組織が硬化して肩の可動域が狭く、症状が進行している何か考えられています。
特に炎症が持続する時は、炎症性サイトカインと呼ばれる物質(インターロイや腫瘍壊死因子など)の作用によって、肩関節周囲の組織にダメージを与えるようです。
(5)内因性の課題(内分泌系、代謝)
糖尿病や甲状腺の問題を抱える患者様は、代謝や内分泌系の異常も肩関節周囲炎の発症リスクを高めることが考えられています。 特に糖尿病患者では、肩関節周囲炎の発症率が一般の人に比べて高くなっています。これにより、代謝異常が肩関節周囲の組織にどのような影響を与えるのかが現在も研究されています。
(6)遺伝的要因
最近の研究では、肩関節周囲炎が家族内で見られるケースが多いことから、遺伝的な要素が関与している可能性も示唆されています。周囲炎を発症しやすい体質を持っている可能性があります。
(7)外的要因(過剰な使用や怪我)
肩の使い過ぎや特定の動作の繰り返し(例えば重いものを持ち上げる仕事やスポーツ)は肩関節の疲労を警戒し、肩関節周囲炎のリスクを高めます。また、過去の肩の怪我や手術経験も関与していると考えられています。
4.肩関節周囲炎の初期の対策と予防法

肩関節周囲炎の初期対策と予防方法として、初期のケアが進行するのを防ぐために重要です。できれば症状が軽いうちに行うべき対策と、予防方法を紹介します。
(1)初期の対策
- 肩の安静を保つ:痛みを感じるときは無理に動かず、しばらく肩を休ませます。
- アイシング(冷却):初期の痛みや炎症がある場合は、患者部を冷やすと効果的です。氷嚢やパッド冷却を使って15〜20分間ていど冷やすと、炎症や痛みが緩和するかもしれません。ただし、冷やしすぎに注意し、繰り返す場合は1時間ほど間隔をあけてください。
- ストレッチと軽いエクササイズ:無理のない範囲で肩周辺のストレッチを行い、関節の可動域を維持します。 具体的には、次のようなストレッチがおすすめです。
・前屈ストレッチ:机の上に腕を置き、体を前に倒し肩をゆっくり伸ばします。
・ペンデュラム運動:痛みが少ない側の手でテーブルを支え、反対側の腕を下げて円を描くようにゆっくり見ます。
- 肩を温める:痛みが治まり始めたら温めて血流を改善します。 入浴や蒸しタオルを使い、患部を温めて筋肉をリラックスさせることをお勧めします。温めることで肩周りの筋肉が柔らかくなり、血行が促進されます。
- 適度な運動:初期段階では、負担の少ない範囲で運動を行うことが重要です。 運動療法の一例としては、腕を肩より少し高く上げて止める「振り子運動」や、壁を伝って手を上げる運動医師や理学療法士の指導のもと、無理のない範囲で行います。
(2)予防方法
- 日常的なストレッチ:肩を定期的に動かすことで柔軟性を維持しましょう。 デスクワークや長時間の作業中にも簡単なストレッチを取り入れましょう。 特に肩甲骨や上腕部をゆっくり伸ばすストレッチが効果的です。
- 肩の柔軟性を高めるエクササイズ:肩関節の柔軟性を考慮して、肩甲骨周りや背中を意識したエクササイズ(例:肩を後ろに回す運動や腕を上げる運動)を行います。 普段から肩周りの筋肉のバランスをよく鍛え、肩が硬くならないようにお気をつけください。
- 正しい姿勢を保つ:長時間の悪い姿勢(猫背や肩が前に出た姿勢)は肩関節に負担をかけやすいです。 デスクワークやスマホの操作時には、肩をリラックスし、正しい姿勢を意識することで肩の負担を軽減します。
- 冷え対策:肩関節の冷え行を悪くし、肩の硬直を考えて、寒い季節には肩周りを冷やさないようにします。柔軟性が保たれやすくなります。
- 適度な負担を避ける:重い物を持ち上げる、肩を徐々に動かすなどの無理な動作は避け、肩に負担な負荷をかけないようにします。日常の作業で肩の負担を感じる場合は、その作業方法を見直すことも大切です。
- 正しい筋力トレーニング:適度な筋力を維持することで肩関節の予防安定性を、肩への負担を減らします。 軽いダンベルなどを使い、肩周りや背中の筋肉を鍛えることが、肩関節のケガにもつながります。
肩関節周囲炎は、予防や初期対応によって進行を遅らせたり防ぐことができる可能性があります。
5.肩関節周囲炎の治し方

肩関節周囲炎(いわゆる「五十肩」)は、肩周囲の筋肉や腱、関節包の炎症により、肩の痛みや動きの制限を伴う症状です。自然に治癒することもありますが、回復には長期間を要する場合もあり、鍼灸治療を含む日常的なケアが重要となります。以下に、鍼灸を取り入れた肩関節周囲炎の改善方法をまとめました。
(1)痛みの強い時期(急性期)
初期で痛みが強い場合は、無理に肩を動かさず、安静にすることが大切です。
鍼治療:炎症部位やその周辺、関連する経穴(ツボ)に鍼をすることで、鎮痛効果や炎症抑制効果、血行促進効果が期待できます。
冷却:熱感や炎症が強い場合は、患部を冷やすことも有効です。冷却時間は10~15分程度を目安にしてください。
(2)慢性期(痛みが落ち着いてきたら)
痛みが軽減してきたら、肩の可動域改善と周囲組織の柔軟性を取り戻すための鍼灸治療が中心となります。
温熱療法:お灸や温かい鍼(温鍼)などで肩を温めることで、血行が促進され、筋肉の緊張が緩み、痛みの軽減につながります。
鍼治療:慢性的な痛みに対して深部の筋肉や関節包、経絡の流れを調整する鍼治療を行います。
灸治療:患部や関連する経穴にお灸をすることで、血行促進、鎮痛、筋肉の緩和などの効果が期待できます。
運動療法:痛みのない範囲で、肩関節の可動域を広げるためのストレッチや軽い運動を行います。
(3)姿勢の改善
姿勢の悪さは肩への負担を増やし、肩関節周囲炎の悪化を招く可能性があります。特にデスクワークなど長時間同じ姿勢での作業は、背筋を伸ばし、肩をリラックスさせる姿勢を心がけましょう。鍼灸治療と並行して、姿勢改善のアドバイスを受けることも有効です。
肩関節周囲炎の改善には、痛みの強い時期には無理なく安静にし、痛みが和らいできたら徐々に鍼灸治療と運動療法を組み合わせて肩を動かしていくことが大切です。専門家のサポートも活用しながら、根気よく続けることが回復につながります。
6.「肩関節周囲炎を治療する!」鍼灸院の選び方

肩関節周囲炎を治療するために鍼灸院を選ぶ際には、鍼灸治療の専門性や実績を考慮し、肩の症状に合った適切な治療が受けられるところを選ぶことが重要です。以下を参考に、信頼できる鍼灸院を選びましょう。
(1)肩関節周囲炎の専門知識と施術経験
肩関節周囲炎の治療に特化した知識や豊富な施術経験を持つ鍼灸師を探しましょう。肩関節の解剖や病態、東洋医学的な見立てを理解した専門家なら、より効果的な治療が期待できます。
(2)実績や評判を確認する
過去に肩関節周囲炎の治療実績が多く、患者からの評判が良い鍼灸院を選ぶと安心です。口コミサイトやSNSなどで患者の声を確認し、肩の症状に特化した治療ができるかをチェックしましょう。最近、Googleのクチコミを操作する治療院が増えています。クチコミの内容も確認してください。
(3)丁寧な診断と治療方針の説明
しっかりと肩の状態を東洋医学的な視点からも診断し、治療方針や施術内容を丁寧に説明してくれる鍼灸院を選びましょう。患者にとって分かりやすい言葉で症状や治療計画を説明し、納得できる治療方針があるか確認することが大切です。
(4)運動療法や生活指導にも力を入れているか
薬は一時的に痛みを感じなくするだけです。根本的な治療を目指しましょう。
肩関節周囲炎の治療には、鍼灸治療だけでなく、運動療法や日常生活での注意点などの指導も重要です。ストレッチや簡単な運動、姿勢改善など、自宅でできるケアについてもアドバイスをしてくれる鍼灸院を選びましょう。
(5)自宅でできるケアのアドバイスがあるか
日常生活での注意点や、自宅でできる簡単なストレッチや運動、お灸の方法など、肩関節周囲炎の再発予防に考えたアドバイスをしてくれる鍼灸院を選びましょう。その後のケアにも役立ちます。
(6)料金体系が明確であるか
肩関節周囲炎の治療は、1回で治ることはないでしょう。
治療費や診療内容の料金が明確に提示されている鍼灸院を選んで安心です。 複数回の通院が必要な場合も多いため、無理なく通える料金体系であることを確認しましょう。
(7)一人ひとりに合わせた治療
肩関節周囲炎は痛みの程度や可動域の制限が人によって異なるため、東洋医学的な体質や状態も考慮した治療プランを提供する鍼灸院を選びましょう。より効果的な改善が期待できます。